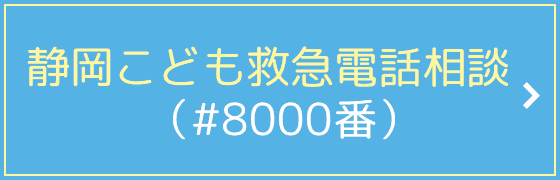当院では、お子様と大人の予防接種をそれぞれ行っております。予約制であり、ワクチン在庫を確認し適切に接種ができる体制をつくるため、ご協力をお願いいたします。
当院ではコロナワクチンを⾏っておりません。
任意接種のおたふくワクチンはお電話か窓⼝での予約になります。
インフルエンザ
2025年度インフルエンザワクチンは予約受付を終了いたしました。
従来の不活化インフルエンザ注射ワクチンの費⽤
| ①小児(富士市在住の1歳から高校3年生該当年齢まで) | 1回 2,650円(富⼠市助成⾦1,000円を差し引いた額) |
|---|---|
| ②高齢者(富士市在住の65歳以上の方) | 1回 1,650円 |
| ③上記以外の⽅(⽣後6ヶ⽉~1歳未満、成⼈、富⼠市以外の⽅など) | 1回 3,650円 |
フルミスト(経⿐弱毒⽣ワクチン)の費⽤
| ①⼩児(富⼠市在住の2歳〜18歳) | 7,000円(富⼠市助成⾦1,000円を差し引いた額) |
|---|---|
| ②上記以外の2歳〜18歳(富⼠市以外にお住まいの⽅) | 8,000円 |
持参頂きたいもの
- 予診票(⾃宅で印刷し事前に記載が可能となりました、院内にご⽤意もしております)
- ⺟⼦⼿帳(上記①の⽅、⽣後6ヶ⽉~1歳未満の乳児)
- 富士市在住が確認できるもの(上記①②の方)
接種に関する注意事項
- 診察とワクチンの同時受診は受け付けておりません。
- インフルエンザワクチン予約枠をご利用ください。
- インフルエンザワクチン専用時間(平日17時15分以降、土曜8時30分〜9時00分)は診療を行っておりません。
- 他ワクチンとの同時接種をご希望の場合は、お電話でご相談ください。コロナワクチンは当院は行っておりません。
- 持ち物のお忘れがないよう、事前準備・確認の上お越しください。時間に遅れないようご来院ください。
<富⼠市在住の⽅>
富⼠市にお住まいのお⼦様の場合、富⼠市こどもインフルエンザワクチンページをご覧ください。
インフルエンザワクチン説明資料、富⼠市こども助成対応の予診票(PDF)、費⽤助成についての内容をご確認いただけます。
フルミストの予約・注意点
在庫なくなり次第終了となりますので、希望の⽅はお早めにご予約をお願いします。
お電話でのフルミストのご質問・ご説明は対応していませんので、ホームページ上の下記2点資料(フルミスト点⿐液ワクチンの説明、フルミスト当院からの説明)を必ず確認していただき、ご理解した上で来院し受付で予約をしてください。費⽤は先払い制であり、お釣りのでないよう現⾦で準備をお願いいたします。
⾼価なワクチンのため、キャンセルされる場合(体調不良での接種⽇電話変更は除く)は、キャンセル料として5,500円をいただきます。ご理解の上、ご予約をお願いいたします。
お子様の予防接種
<ご確認ください>
プライバシー保護と医療安全の観点から、院内での写真・動画撮影はご遠慮させていただきます。
2025年4⽉以降の予防接種変更点は、ホームページのご確認をお願いします。
富⼠市情報は下記に掲載しております。他⾃治体にお住まいの⽅は、各⾃治体の担当部署にご相談・ご確認をお願いいたします。
現在、⽇本脳炎ワクチン(3歳未満)とおたふくワクチン(任意)のご予約は、お電話でのみおこなっております。
ホームページ情報をご確認後、ご予約をご相談ください。
現在、日本脳炎ワクチン接種時間帯は、3歳未満の方は平日11時予約枠のみとさせていただいておりますが、ご都合が合わない方はお電話でご相談ください。
3歳以上の方は、平日11時、16時、16時半枠でネット予約可能です。
各ワクチンのご予約について、ネット予約画面にてご希望の日・時間帯の枠が埋まってしまっている場合は、お電話でご相談ください。
乳幼児は抵抗力が未熟
赤ちゃんや幼児は病気に対する抵抗力が未熟ですし、母親から授かった免疫(抵抗力)も生後数ヶ月が経過すれば弱まってきます。そうすると赤ちゃんの体は病気(感染症)に罹りやすくなってしまいます。病気に罹ってしまうと、重い後遺症が残ったり、生命の危険にさらされたりすることもあります。
生後約2ヶ月がワクチンデビュー
そうした事態を未然に防ぐために必要になってくるのが、病原体(ウイルスや細菌)に対する免疫をつくり出すワクチンの接種、つまり予防接種です。
予防接種は病気(感染症)に罹らないよう、またたとえ罹っても症状がひどくならないように実施します。一般的には生後約2ヶ月がワクチンデビューのタイミングです。
当院では、お子様の予防接種を行っておりますので、ご予約の上、接種をお受けください。
「個別ワクチンスケジュール」を計画します
現在の日本には数多くの予防接種があり、「どれを接種したらよいのか?」と戸惑われる保護者の方も少なくないと思います。それに予防接種のスケジュール管理は、一般の方には少々難しいものです。そんなスケジュール管理についても、ご相談ください。お子様一人一人の「個別ワクチンスケジュール」を計画いたします。
お持ちいただくもの
- 予防接種予診票
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- こども医療受給者証
- 診察券(お持ちの方)
- など
※受診の前に、ご自宅で体温を測定してください。熱がある場合はお電話してください。
※接種当日はいつも通りの生活をして構いませんが、激しい運動は避けてください。接種後、体調の変化が見られた際は、すぐに医師にご相談ください。
定期接種と任意接種
予防接種には、以下に記すように「定期接種」と「任意接種」の2種類があります。
定期接種
国が「一定の年齢になったら受けるように努めなければいけない」(接種の勧奨)と規定しているワクチンです。
接種費用は対象年齢内・規定回数内であれば、基本的に公費で負担されます(対象年齢や規定回数を超えたり、指定の医療機関以外で受けたりした場合の接種費用は、全額自己負担となります)。
| ワクチン | 標準的接種期間 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 5種混合(4種混合+ヒブ)不活化ワクチン | ⽣後2ヶ⽉〜7歳6ヶ⽉未満 | 1~4回 (2024年4⽉から定期接種開始) |
| ヒブワクチン不活化ワクチン | 生後2ヶ月~5歳未満 | 1~4回 (接種開始年齢によって異なります) |
| ⼩児肺炎球菌ワクチン(15価・20価) | 生後2ヶ月~5歳未満 | 1~4回 (接種開始年齢によって異なります) |
| 4種混合ワクチン不活化ワクチン | 生後2ヶ⽉〜7歳6ヶ⽉未満 | 4回 (2025年途中に製造販売中⽌) |
| 3種混合ワクチン(任意)不活化ワクチン | 生後3ヶ月~7歳6ヶ月未満 | 4回 |
| 不活化ポリオワクチン(任意)不活化ワクチン | 生後3ヶ月~7歳6ヶ月未満 | 4回 |
| 2種混合ワクチン不活化ワクチン | 11歳~13歳未満 | 1回 |
| 水痘ワクチン生ワクチン | 1歳~3歳未満 | 2回 |
| BCGワクチン生ワクチン | 生後5ヶ月~8ヶ月未満 | 1回 |
| MR(麻疹・風疹混合)ワクチン生ワクチン | 1回目1歳~2歳未満 2回目小学校就学前1年間内 |
2回 |
| 日本脳炎ワクチン不活化ワクチン | ⽣後6ヶ⽉〜 (富⼠市2025年4⽉から⽣後6ヶ⽉以降 接種開始可能、⾃治体毎で異なる) |
4回 |
| 子宮頸がんワクチン不活化ワクチン | 中学1年生~ | 3回 |
| B型肝炎 | 生後2ヶ月~ | 3回 |
| ロタリックス(ロタウイルスワクチン) | 生後2ヶ月〜24週 | 2回 |
| ロタテック(ロタウイルスワクチン) | 生後2ヶ月〜32週 | 3回 |
任意接種
定期接種以外の予防接種です。「任意」とは、受けなくても良い予防接種といった意味合いではありません。費⽤は基本的に⾃費(もしくは助成以外の部分的⾃費負担)になりますが、それでもやはり接種を受けられるよう、お勧めいたします。
| ワクチン | 標準的接種期間 | 接種回数 |
|---|---|---|
| おたふくかぜワクチン生ワクチン | 1歳~ | 2回 |
| インフルエンザワクチン不活化ワクチン | 満1歳から13歳未満まで | 2回 |
| 13歳以上 | 1回 |
<おたふくワクチンは、2025年4⽉から富⼠市住⺠登録がある1歳児〜年⻑児までを対象に、1回2,000円 2回まで助成を受けることができます。>
⼀般的には1回⽬ 1歳、2回⽬ 5〜6歳の年⻑児が推奨されます。
費⽤(2025年4⽉時点):7,500円/回(富⼠市助成対象の⽅は5,500円/回)
接種当⽇に受付で現⾦のみの⽀払いになります。
集団生活に入る前に
保育園や幼稚園などの「集団生活」に入ると、ウイルスなどの病原微生物に接する機会が急増します。
入園前には、お子様の接種状況を確認し直し、「接種漏れ」や「任意接種」などについては、可能な範囲で受けておくようにすると良いでしょう。
子宮頸がんワクチン
9価HPVワクチンの定期接種化について
令和5年(2023年)4月1日より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種ワクチンに追加されます。
4価のガーダシル(HPV6/11/16/18型)に比べ、さらに5種類のHPV(31/33/45/52/58型)への感染予防効果が期待されます。
キャッチアップ接種については、下記の「富士市 予防接種 子宮頸がんワクチン キャッチアップ」の最新内容をご確認ください。
接種回数は、初回接種が15歳以上は3回、15歳未満は2回でも可となりました。
3回接種(①②③)
①、② (①から2ヶ月後)、③ (①から6ヶ月後)、または①、②( ①から1~2ヶ月後)、③ (②から3~4ヶ月後)
2回接種(①②)
①、② (①から5~12ヶ月後) *②を①の5ヶ月より前に接種した場合は3回目が必要になります。
体の負担の少ない2回接種で可能な中学1年生〜15歳未満でワクチンをスタートすることをお勧めします。
2023年4月から予約枠を平日17時・土曜9時30分で決まった枠数で接種を開始致します。今後の接種希望相談数の状況により適宜枠数を変更していく予定です。
予診表をお持ちの方は、お電話で予約相談をお願いいたします。
接種時の持ち物は、「HPVワクチン接種予診表と母子手帳」になります。
接種後は、30分間の院内待機が必要となります。
また、接種対象外の方で自費接種の場合、下記価格(税込)となっております。
| ガーダシル(4価ワクチン) | 1回 17,000円、3回の接種で計 51,000円 |
|---|---|
| シルガード(9価ワクチン) | 1回 29,000円、3回の接種で計 87,000円 |
子宮頸がんについて
子宮頸がんの発生にはヒトパピローマウイルス(Human Papilloma virus : HPV)と呼ばれるウイルスが関わっています。このウイルスは、子宮頸がんの患者様の90%以上で見つかることが知られており、HPVが長期にわたり感染することで、「がん」になると考えられています。20〜30代の若い女性に増加しています。
生涯にHPV感染する確率は80%以上であり、通常ウイルスが自然に身体から排除されます。しかし、ウイルスが自然に排除されず、長い間持続的に感染した場合には、細胞ががん細胞に変化することがあります。
子宮頸がんの予防法としては、HPVワクチン接種と検診(20歳以上の女性に推奨)が大切になります。
子宮頸がんワクチンで予防
ヒトパピローマウイルス(Human Papilloma virus : HPV)は200種類以上の型があり、子宮頸がんの約65%が16型と18型が占めています。20〜30代で発見される子宮頸がんの80~90%はこの型になります。そのため、中学1年生〜高校1年生相当が対象となっていま
す。現在医療機関で使用されているワクチンはいずれもこの型に対する予防のワクチンになります。2023年4月よりシルガード9が助成適応ワクチンに加わります。
※ワクチンに関しては、下記をご参照ください。